※携帯・PHSからもご利用になれます
- 受付時間
- 【平日】9:30~20:00

2021-05-25 14:30:00
ORAI1遺伝子多型を発見2016年1月21日、理化学研究所の尾内善広客員研究員、田中敏博グループディレクターらの共同研究チームは、川崎病の発症にはORAI1遺伝子の遺伝子多型が関与していることを解明したと発表。 今回の研究成果はアメリカの科学雑誌「PLOS ONE」にて…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
上級者向けの研修国際医療技術財団(JIMTEF/ジムテフ)、国立病院機構災害医療センター、国際開発救援財団(FIDR/ファイダー)の主催により、2月21日(日)、「第4回JIMTEF災害医療研修アドバンスコース」が開催される。 日本臨床衛生検査技師会では受講者を募集して…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
非侵襲の血糖値測定方法2016年2月2日、東北大学の松浦祐司教授の研究グループは遠赤外線を用いた非侵襲の血糖値測定方法を開発したと発表。この方法が実用化されると遠赤外線を照射するだけで血糖値を測定することが可能になる。 同研究グループは小型で低価格なヘ…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
メチオニン代謝が影響東京大学の樫尾宗志朗大学院生、小幡史明特任助教(現在はイギリス The Francis Crick Institute研究員)、三浦正幸教授らの研究グループはショウジョウバエの成虫原基を用いて、損傷組織の修復を損傷部分から離れた組織がコントロールするシステム…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
世界で初めての発見2016年2月3日、新潟大学の河内泉講師、西澤正豊教授らの研究グループは多発性硬化症および視神経脊髄炎による神経障がいには異常なミトコンドリアの集積が関与することを発見したと発表。 今回の研究成果は「ANNALS OF NEUROLOGY」にて公開されて…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
線虫C.elegansを用いた実験で明らかに2016年2月4日、鳥取大学の河野強教授、東京都健康長寿医療センター研究所の老化制御研究チームおよび本田修二研究員、アメリカのエモリー大学のGuy M Benian教授らの研究グループは線虫C.elegansを用いた実験によって、生育状況…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
脳の線維束を見つけやすくする方法2016年2月5日、国立研究開発法人情報通信研究機構の竹村浩昌特別研究員らの研究グループは脳のMRI画像から神経線維束を見つけやすい「アンサンブルトラクトグラフィー法」という方法を開発したと発表。 この技法は全く新しい方法な…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
造血幹細胞の可視化に成功2016年2月11日、東京大学の山崎聡助教、中内啓光教授(スタンフォード大学兼任)、米国スタンフォード大学のJames Y.Chen、宮西正憲研究員、Irving Weissman教授らの共同研究グループは骨髄内に存在する造血幹細胞の可視化に成功したと発表。 …
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
世界初となる発見2016年2月9日、筑波大学の渋谷彰教授、小田ちぐさ助教らの研究チームは粘膜の死細胞が免疫細胞を刺激しアトピー性皮膚炎や腸炎、喘息の発作を促すことを発見したと発表。 この研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構における研究開発の一環と…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
共同研究の成果2016年2月11日、基礎生物学研究所は藤田保健衛生大学、生理学研究所、富山大学と共同研究によって、RNG105遺伝子のヘテロ欠損がいくつかの行動特性の発現に関与していることが明らかになったと発表。 いくつかの行動特性とは、社会性の低下や状況変化…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
ADCC活性の新測定方法を開発2016年2月15日、国立研究開発法人国立がん研究センターはがん患者の免疫状態、ADCC活性の新測定方法を開発したと発表。 ADCC活性とは抗体依存性細胞傷害活性の略。抗体をがん細胞に結合させることで免疫細胞をその周囲に呼び寄せ、集合し…
続きを見る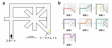
2021-05-25 14:30:00
初期学習に関する研究2016年2月17日、東京大学の池谷裕二教授らの研究グループはマウスを用いた実験によって、初期学習を失敗すればするほど成績が伸びることを発見したと発表。 今回の研究成果はイギリスの科学誌「Scientific Reports」において公開されている。 …
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
医療事故情報収集等事業公益財団法人日本医療機能評価機構が実施している医療事故情報収集等事業において、2月15日、医療安全情報NO.111「パニック値の緊急連絡の遅れ」が公表された。 この情報は、第42回報告書をもとに作成されたもので、集計期間は2012年1月1日?…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
新規オーファンGPCRを発見2016年2月18日、京都大学の土居雅夫准教授、岡村均教授らの研究グループは体内時計を調節する新規オーファンGPCRを発見したと発表。 今回の研究成果はイギリスの科学誌「Nature Communications」に掲載されている。 視交叉上核に着目生…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
褐色脂肪細胞に関する新たな発見2016年2月19日、生理学研究所の富永真琴教授、内田邦敏助教、Sun Wuping研究員、京都大学の河田照雄先生、国立循環器病研究センターの岩田裕子先生らの研究グループは褐色脂肪細胞のTRPV2チャネルが効率よく脂肪を燃焼させることを発見…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
大腸がんに関する研究2016年2月19日、九州大学の三森功士教授、東京大学の新井田厚司助教、宮野悟教授、大阪大学の森正樹教授らで構成される研究チームは、大腸がんは多様な遺伝子変異を持ったばらつきのある細胞で構成されていることを発見。 また、この不均一性は…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
別種の神経細胞に変化2016年2月23日、慶應義塾大学の大石康二講師、仲嶋一範教授らの研究チームはマウスを用いた実験で、子宮内胎児における大脳皮質の神経細胞を本来とは異なる位置に配置すると、本来とは異なる性質の神経細胞に変化することを発見したと発表。 今…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
病理組織技術についての研修一般社団法人宮城県臨床検査技師会では、5月7日(土)、「平成27年度宮臨技病理部門精度管理フォローアップ研修会」を開催する。昨年実施された精度管理調査をもとに、病理組織技術についての研修をおこなう。 【日時】平成28年5月7日(土…
続きを見る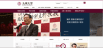
2021-05-25 14:30:00
8-オキソグアニンが神経突起の変性に関与2016年2月25日、九州大学の中別府雄作主幹教授が率いる研究グループは神経突起の変性には8-オキソグアニン(以下、8-oxoG)の蓄積が関与していることを見いだしたと発表。 今回の研究成果はイギリスの科学誌「Scientific Repor…
続きを見る※携帯・PHSからもご利用になれます
検査技師人材バンクは、臨床検査技師の方のお仕事探しや就職・転職を無料でサポート致します。
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信を禁じます。