※携帯・PHSからもご利用になれます
- 受付時間
- 【平日】9:30~20:00
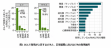
2021-05-25 14:30:00
肝臓がんの病態を解明2015年10月29日、理化学研究所のピエロ・カルニンチ チームリーダー、橋本浩介研究員らの研究グループは、肝細胞がんではレトロウイルスに由来したRNAの発現が活性化していることを発見し、その活性が再発率およびがんの分化度などに関係している…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
新たな発見国立研究開発法人情報通信研究機構の未来ICT研究所は低窒素環境において分裂酵母細胞を培養し、その時の遺伝子発現レベルの変化を独自に改良したDNAマイクロアレイによって計測。その結果、リボソームタンパク質遺伝子の発現レベルが培養環境によって変化す…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
国際共同研究の成果2015年11月6日、京都大学の岩田想教授、長崎国際大学の濱崎直孝教授らの研究チームは赤血球において酸素輸送を担う膜タンパク質の立体構造を明らかにしたと発表。 この研究はJST戦略的創造研究推進事業からの支援を受けて実施された。また、この…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
トランスフェリンがDNAを損傷2015年11月11日、東北大学の八重樫伸生教授、豊島将文助教らの研究グループは卵胞液中のトランスフェリンが卵管上皮細胞のDNA損傷に関与していることを発見したと発表。 今回の研究成果は、11月9日にがんの基礎研究を掲載している「Onco…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
日周性酵素活性の振動機構を発見2015年11月13日、東邦大学の田丸輝也講師と東京大学の小澤岳昌教授らの研究チームは哺乳類の体内時計を働かせる日周性酵素活性の振動機構を発見したと発表。 同研究チームはマウスの脳や肝臓、皮膚の細胞および組織を使った実験で、…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
椎間板変性抑制効果を発見2015年11月12日、慶應義塾大学の松本守雄教授、中村雅也教授、藤田順之助教らの研究チームはラットを用いた実験によって、過度なストレスを除去もしくは取り去る物質である抗酸化剤N-アセチル システインに椎間板変性を抑える効果があることを…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
新たな原因遺伝子を発見2015年11月13日、東北大学の新堀哲也准教授、青木洋子教授、笹原洋二准教授、中山啓子教授、宮城県立こども病院の今泉益栄科長らの研究グループは、無巨核球性血小板減少症と橈尺骨癒合症を合併する疾患の新たな原因遺伝子を発見したと発表。 …
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
共同研究の成果2015年11月19日、東北大学の大隅典子教授、片桐秀樹教授、酒寄信幸元研究員らは妊娠中のマウスにオメガ6脂肪酸過多かつオメガ3脂肪酸欠乏飼料を与えると、仔マウスの大脳新皮質の神経細胞数が減少することを発見したと発表。 この研究は理化学研究所…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
先端的な研究方法2015年11月20日、熊本大学の西山功一特任講師/主任研究員、東京大学の栗原裕基教授、杉原圭学部生らの研究グループは、血管新生の際に血管が伸びる時の血管内皮細胞の運動をコントロールする仕組みを生物学と数理モデル・コンピュータシミュレーショ…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
改善方法も発見2015年11月20日、九州大学の中島欽一教授とBerry Juliandi学術研究員らは東北大学や星薬科大学、国立医薬品食品衛生研究所と共同研究を実施し、妊娠マウスに抗てんかん薬のバルプロ酸(以下、VPA)を投与すると生まれた仔マウスの脳において神経細胞の産生…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
前駆脂肪細胞のエピゲノム解析の結果2015年11月20日、東京大学の酒井寿郎教授、松村欣宏助教らの研究グループは前駆脂肪細胞のエピゲノムを解析することで、脂肪を蓄える遺伝子の働きを抑制する新規のクロマチン構造を発見したと発表。 今回の研究成果は国際科学誌…
続きを見る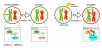
2021-05-25 14:30:00
京大の快挙2015年11月24日、京都大学の奥田博史特定助教、横山明彦特定准教授らの研究グループは、MLLキメラタンパク質がSL1タンパク質複合体を利用して白血病を発症させていることを発見したと発表。 これまでの研究では、MLLキメラタンパク質が白血病の原因である…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
新規化合物を開発2015年11月26日、東北大学の阿部高明教授らは岡山理科大学の林謙一郎教授、自治医科大学の小坂仁教授、筑波大学の中田和人教授らと共同研究によって、ミトコンドリア病の進行を抑制するMA-5という新規化合物を開発したことを発表。 今回の研究成果…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
「CKX-CCSW」発売2015年12月2日、オリンパス株式会社は生物顕微鏡によって培養容器中に存在する細胞の数や単位面積当たりの細胞密度を計測する時に用いる細胞密度計測ソフトウエア「CKX-CCSW」の発売を発表した。 近年益々再生医療の研究が熱を帯びてきている。2013…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
がん細胞の運動を抑えるKeap12015年12月2日、理化学研究所の吉田稔主任研究員、伊藤昭博専任研究員らの共同研究グループは酸化ストレス応答転写因子であるNrf2を制御するKeap1ががん細胞の運動を抑える機能を有することを発見したと発表。 今回の研究成果はアメリカ…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
研究成果を発表2015年12月3日、松谷化学工業株式会社はラットにおけるプシコースやタガトース、ソルボースが脂質代謝に及ぼす影響についての研究成果を11月28日から29日に開催された一般社団法人日本食物繊維学会の第20回学術集会にて口頭発表を行ったと発表。 この…
続きを見る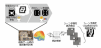
2021-05-25 14:30:00
場面予測を解読2015年12月4日、京都大学の鹿内友美大学院生と石井信教授は迷路ゲームに参加する人の脳活動を計測することで、予測した場面の解読に成功したと発表。 この研究は株式会社国際電気通信基礎技術研究所と共同で実施されたものであり、今回の研究成果は国…
続きを見る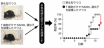
2021-05-25 14:30:00
神経難病、多発性硬化症2015年12月9日、東京大学のMatteo M.Guerrini学術支援職員(研究当時)や岡本一男助教、高柳広教授らの研究チームは多発性硬化症が起こる仕組みを解明したと発表。 今回の研究成果はアメリカの科学誌「Immunity」にて公開された。 欧米では…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
6つの疾患領域で研究開始2015年12月15日、京都大学のiPS細胞研究所と武田薬品株式会社はiPS細胞技術を臨床応用するために6つの共同研究をスタートさせたと発表。今回の共同研究は、がんや神経変性疾患、心不全、難治性筋疾患、糖尿病などにおいてiPS細胞技術をいかにし…
続きを見る※携帯・PHSからもご利用になれます
検査技師人材バンクは、臨床検査技師の方のお仕事探しや就職・転職を無料でサポート致します。
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信を禁じます。