※携帯・PHSからもご利用になれます
- 受付時間
- 【平日】9:30~20:00

2021-05-25 14:30:00
共同研究の成果2015年11月19日、東北大学の大隅典子教授、片桐秀樹教授、酒寄信幸元研究員らは妊娠中のマウスにオメガ6脂肪酸過多かつオメガ3脂肪酸欠乏飼料を与えると、仔マウスの大脳新皮質の神経細胞数が減少することを発見したと発表。 この研究は理化学研究所…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
国際共同研究の成果理化学研究所の林茂生が率いる多細胞システム形成研究センター形態形成シグナル研究チームと大谷哲久テクニカルスタッフらの国際共同研究チームは2015年6月23日、細胞伸長の司令塔が細胞の伸長端に配置される仕組みを解明したと発表。 細胞伸長の…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
腸炎を抑えるメカニズムを解明2015年7月1日、慶應義塾大学医学部の吉村昭彦教授率いる研究グループは金井隆典教授率いる研究グループと共同研究を行い、ペプチドグリカンが免疫調節タンパク質と免疫制御細胞を誘導することで腸炎を抑えるメカニズムを解明したと発表。 …
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
共同研究による成果2015年7月2日、理化学研究所と国立循環器病研究センターの共同研究グループはQT延長症候群の発症にカルモジュリン結合遺伝子が関与している可能性があると発表。 同研究チームは理研の田中敏博グループディレクター、角田達彦グループディレクタ…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
次世代がん研究シーズ戦略育成プログラムの一環2015年7月3日、東京大学の滝田順子准教授、油谷浩幸教授、京都大学の小川誠司教授らの共同研究チームは横紋筋肉腫における遺伝子異常や構造変化、DNAメチル化異常の全体像を明らかにしたと発表。 今回の研究成果は英国…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
天然構造の形成に迫る2015年7月7日、理化学研究所の研究チームは数マイクロ秒で起こるタンパク質分子の構造変化を解析するための新しい手法を開発したと発表。 人間だけでなく、すべての生物はたくさんの細胞によって形成されている。細胞の約70%は水分で約15%は…
続きを見る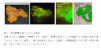
2021-05-25 14:30:00
ヒトの乳腺腫瘍が光る2015年7月13日、東京大学の浦野泰照教授が率いる研究グループは以前開発した、がん細胞において活性が上昇するガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼというタンパク質分解酵素の検出を可能にする蛍光プローブの有用性を検証したことを発表。 …
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
マウスを用いた実験で解明カリフォルニア大学の小宮山尚樹アシスタント・プロフェッサー、牧野浩史博士は2015年7月14日、マウスを用いた実験で学習が脳内の情報処理形態をどのように変化させるのかを明らかにしたと発表。 この研究はJST戦略的創造研究推進事業にお…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
胃潰瘍症状を緩和2015年7月16日、大阪府立大学の中野長久客員教授と株式会社ユーグレナの共同研究チームは微細藻類ユーグレナ(以下、ユーグレナ)の粉末を継続的に摂取すると胃潰瘍症状を緩和すると発表。 今回はラットを用いた実験で、ユーグレナ粉末を混ぜた餌、ア…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
ついにTrimmerを発見2016年2月26日、東京大学の泉奈津子助教と泊幸秀教授らの研究グループはこれまでに存在は予測されていたものの同定に至っていなかったタンパク質「Trimmer」を発見。 それだけでなく、piRNAが持つ機能を発揮するにはTrimmerとPapiがpiRNAを成熟…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
共同研究の成果2016年2月11日、基礎生物学研究所は藤田保健衛生大学、生理学研究所、富山大学と共同研究によって、RNG105遺伝子のヘテロ欠損がいくつかの行動特性の発現に関与していることが明らかになったと発表。 いくつかの行動特性とは、社会性の低下や状況変化…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
生体内で可視化2016年1月12日、理化学研究所の岡田峰陽チームリーダー、北野正寛客員研究員、和歌山県立医科大学の改正恒康教授らの共同研究グループは生体内においてキラーT細胞に重要な樹状細胞を可視化することに成功したと発表。 今回の研究成果はアメリカの科…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
ルシフェラーゼを利用2015年10月23日、東京大学の浦野泰照教授と慶應義塾大学の小林英司特任教授の共同研究チームは、生きた動物の体内において微量に発生する活性酸素をルシフェラーゼによって検出する方法を開発したと発表。 今回の研究成果はドイツの科学雑誌「A…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
新たな方法を開発2015年10月23日、理化学研究所と京都大学の共同研究グループは生体外で多能造血前駆細胞を無限に増幅させる方法を開発したと発表。 今回の研究成果はアメリカの科学雑誌「Stem Cell Reports」において公開された。 これまでの研究骨髄内の造血幹…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
共同研究の成果2015年10月23日、筑波大学の林悠助教らと理化学研究所の糸原重美チームリーダーらの共同研究チームは脳においてレム睡眠とノンレム睡眠を切り替えている部位を特定したと発表。 さらに、レム睡眠を操作可能なトランスジェニックマウスを開発し、レム…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
3つの遺伝子領域発見2015年10月22日、理化学研究所の田中敏博グループディレクター、尾崎浩一上級研究員らの共同研究グループは閉塞性動脈硬化症の発症に関する遺伝子領域を発見したと発表。 これまでの研究によって、閉塞性動脈硬化症の発症に遺伝的要因が関係する…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
非環式レチノイドの作用メカニズム解明2016年1月8日、理化学研究所の小嶋聡一特別ユニットリーダーらの研究グループと今本尚子主任研究員、東京医科歯科大学の影近弘之教授らの共同研究グループは肝がん再発予防薬として臨床試験が進められている「非環式レチノイド」…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
線虫C.elegansを用いた実験で明らかに2016年2月4日、鳥取大学の河野強教授、東京都健康長寿医療センター研究所の老化制御研究チームおよび本田修二研究員、アメリカのエモリー大学のGuy M Benian教授らの研究グループは線虫C.elegansを用いた実験によって、生育状況…
続きを見る
2021-05-25 14:30:00
別種の神経細胞に変化2016年2月23日、慶應義塾大学の大石康二講師、仲嶋一範教授らの研究チームはマウスを用いた実験で、子宮内胎児における大脳皮質の神経細胞を本来とは異なる位置に配置すると、本来とは異なる性質の神経細胞に変化することを発見したと発表。 今…
続きを見る※携帯・PHSからもご利用になれます
検査技師人材バンクは、臨床検査技師の方のお仕事探しや就職・転職を無料でサポート致します。
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信を禁じます。